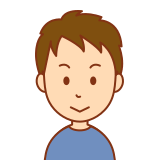
職場でも、家族の介護をしていても、つい「イラッ!!!」としてしまうことありませんか?
今回は、【観察】スキル(技能)の向上と”イライラ”対策を一石二鳥で取り組むお話しです。
※ ”イライラ”を0(ゼロ)にする方法では、ありません。
あくまでも、「減らす」作業です。ご了承ください。
結論:【観察】は”イライラ”と負の感情を減らす事にも利用できる
理由を説明する前に、イライラを観察するとできるようになることがあります。
- イライラする原因へがわかり、対処方法が見つけられる
- イライラしている自分の気持を切り離して冷静になりやすくなる
- 似たような状況に遭遇した時に、スムーズに対処できる(スキルアップしている)
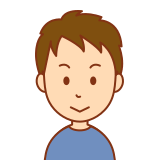
まずは、”イライラ”するのは、どんな時なのかを思い出してみましょう。
”イライラ”の原因を探る
イライラを感じやすいとき
人が”イライラ”を感じるのは、主に次のようなときかと思います。
- 忙しい時
- 周囲の人が予想と違う言動をした時
- 自分自身が失敗した時
どれか、一つくらいは思い当たる場面を思い出すのではないでしょうか。
1.忙しい時
おそらく、ほとんどの人は一番の理由かと思います。
仕事の場合は、
- 一日の業務量に対して職員数が足りずに時間までに終わらない。
- 職員はいるけど業務量が多すぎる。または、動ける職員がいない。
家族の介護の場合は、
- 掃除や洗濯、買い物など家事をする時間が作れない。
- 朝から晩まで、付きっきりで眠る暇がない。
- 自分の時間が全く無い。
と、いった理由から、身も心も余裕がなくなって”イライラ”いきます。
2.周囲の人が予想と違う言動をした時
予想=期待と言い換えても良いかもしれません。
- オムツ交換を頼んだはずの職員が壁の装飾をしている。
- 「待ってて」と言っておいたはずなのに、利用者(家族)が勝手に歩いて転んでいる。
相手に望んだ物事と結果がズレていることから生じている”イライラ”です。
3.自分自身が失敗した時
自分自身の目標や想定と現実が合わない時に感じやすいと思います。
- 上手く移乗介助できるはずだったのに、転ばせてしまった。
- 問い合わせへの対応が上手くできず文句を言われた。
自分自身に問題があるのかどうかに疑問を感じたり、「他人から使えない人」と評価されたりすることを恐れて責任の所在を周囲に求めて”イライラ”します。
もっと、詳しいことは「メンタルヘルス」のテクニックに関わることなので、ここでは割愛します。
イライラする原因に共通すること
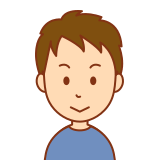
1.~3.に共通するのは、「他人や周囲と自分」を比較している結果、”イライラ”していることが殆どだって事が言えると思います。
つまり、周囲の環境や人物が自分自身の望んでいる”理想”に沿っているとイライラしにくくなります。
これは、自分自身の言動に対しても同じことが言えます。
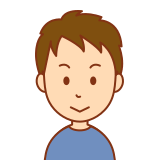
ここまでは、”イライラ”する理由についてでした。
次は、観察がどんなものだったかを思い出してみます。
観察は起きた事柄そのものと、起きた原因や背景を探り当てて読み解くもの
観察は、
- 予測
- 実証
- 結果
- 考察
から、成り立ちます。
もう少し噛み砕いて書いている記事です。
観察の基本は「なぜ?」から
観察を始めようとしたときに、「そうしたかったから」で終わってしまっては、何も探求できなくなってしまいます。
- 相手のいる事柄であるならば、
- 「なぜそう考えるのか?」
- 「何のためにしているのか?」
と、理由の背景に視点を深めていきます。
仮に、認知症の方だとしても思考を辿る作業は一度、行っておかないと「症状だから」と短絡的になってしまう恐れもあります。
※ ここで、認知症の方を例に挙げましたが、決して暴力などの迷惑行為を無条件に肯定するつもりはありません。むしろ、しっかりと調べて必要に応じて医療機関の受診などの対応が必要な場合があると強く感じています。
「なぜ?」と様々な疑問を持つことが、予測につながる
予測がなければ、その後に行う実証などにつながることが無くなってしまいます。
他の記事にも書いていますが一度観察を行うと、新しい疑問と仮説が浮かんできて観察の思考回路を作ることができるようになります。
また、観察するためには『客観的な視点』を持つ必要があります。
客観的な視点を持つということは、”イライラ”している
自分自身の感情と現在を切り離すことになるので、
一時的に感情を落ち着けることができるようになります。
原因が予測できれば、対策を見つけられる
ある程度、原因が見えてくると今度は”イライラ”への対策を立てることができるようになります。
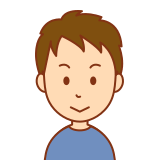
状況への対応力が向上しているということは、
様々な場面に対するスキルアップができていると言い換えることができます。
ただし、対策を立ててもどうにもできないこともあります。
- 基本、相手をかえることはできない
- 環境を変えることには限度がある
この二つは、どんなに場面に対するスキルが向上しても難しいです。
相手の考えを変えようとしたり、周辺の変えられないような環境を無理して変えるくらいであれば、
自分自身の観察や対応するためのスキル(技能)を磨いて行く方が、
労力は少なく済みます。
まとめ
”イライラ”した時は、対象や起きたことを観察し背景を探る
客観的な視点で観察することで、感情を切り離すことができる
結果として、”イライラ”した時に観察すると負の感情を減らすことができる
同じような状況への対策も作れるためスキルアップにもつながる
日常のあらゆる場面をスキルアップの練習と捉えることで、介護の大変さや辛さが少しでも「軽く」なる人が増えて欲しいです。
おまけ
特に自宅で家族を介護する人には、多少”おせっかい”と言われても伝えて欲しい事です

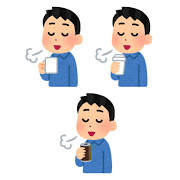

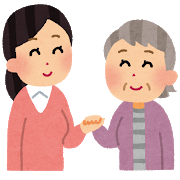

コメント